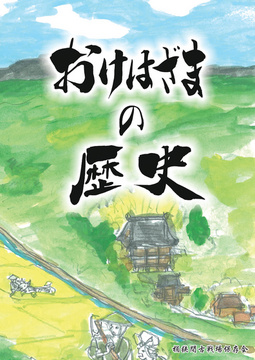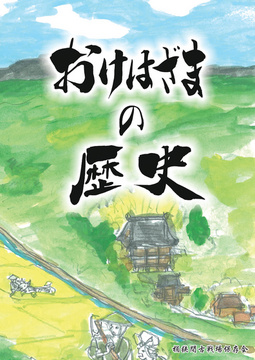おけはざまの歴史

- ページ: 8
- 5. 戦国時代
戦国時代の勢力図(1550 年代)
1460 年頃、 室町幕府が衰退して将軍家と守護大名の家督争いが戦争に発展し、 応仁の乱 (1467 年~ 1477 年)となり、それ以後各地の豪族が覇権争いをすることとなりました。身分の下位 の者が上位(守護代・地頭・国人)をしのいでのし上がる下克上がおこりました。そして武力 で領土を拡大する群雄割拠の戦国時代になりました。その後、今川と織田の抗争は 1540 年頃 から西三河の支配権をめぐって争いが始まっていました。
守護: 国(領土)ごとに置かれて御家人の監督や軍事警察にあたった役目 地頭: 荘 園や国司が支配する領土で土地の管理、年貢の取りたてにあたる役目 国人: 土着の武士
こくじん じとう しょうえん こ く し ねんぐ
し ゅ ご に し み か わ し は い け ん あらそ ぐんゆうかっきょ こうそう し ゅ ご だ い じ と う こくじん げこくじょう ごうぞく は け ん
すいたい
か と く あらそ
おうにん
らん
ごけにん
かんとく
これらの役人は強い権力を持っていたんだわん
8
�
- ▲TOP