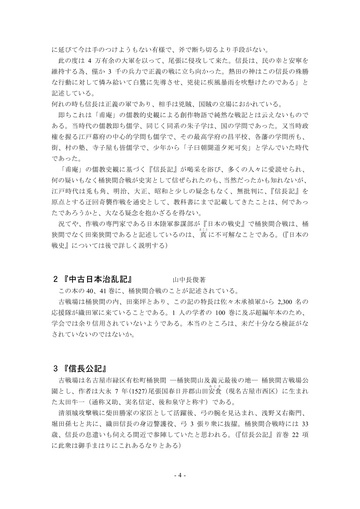桶狭間合戦始末記
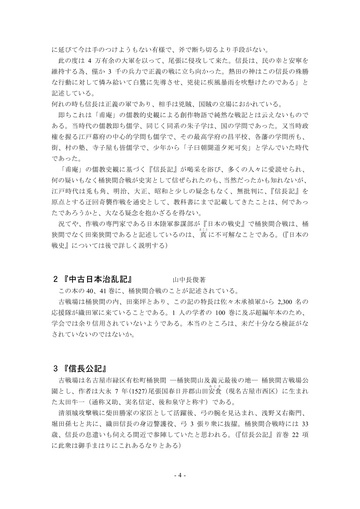
- ページ: 4
- に延びて今は手のつけようもない有様で、斧で断ち切るより手段がない。 此の度は 4 万有余の大軍を以って、尾張に侵攻して来た。信長は、民の幸と安寧を 維持する為、僅か 3 千の兵力で正義の戦に立ち向かった。熱田の神はこの信長の殊勝 な行動に対して憐み給いて白鷺に先導させ、兇徒に疾風暴雨を吹懸けたのである」と 記述している。 何れの時も信長は正義の軍であり、相手は兇賊、国賊の立場におかれている。 即ちこれは「甫庵」の儒教的史観による創作物語で純然な戦記とは云えないもので ある。当時代の儒教即ち儒学、同じく同系の朱子学は、国の学問であった。又当時政 権を握る江戸幕府の中心的学問も儒学で、その最高学府の昌平校、各藩の学問所も、 街、村の塾、寺子屋も皆儒学で、少年から「子曰朝聞道夕死可矣」と学んでいた時代 であった。 「甫庵」の儒教史観に基づく『信長記』が喝采を浴び、多くの人々に愛読せられ、 何の疑いもなく桶狭間合戦が史実として信ぜられたのも、 当然だったかも知れないが、 江戸時代は兎も角、明治、大正、昭和と少しの疑念もなく、無批判に、 『信長記』を 原点とする迂回奇襲作戦を通史として、教科書にまで記載してきたことは、何であっ たであろうかと、大なる疑念を抱かざるを得ない。 況てや、作戦の専門家である日本陸軍参謀部が『日本の戦史』で桶狭間合戦は、桶
まこと
狭間でなく田楽狭間であると記述しているのは、 真 に不可解なことである。 ( 『日本の 戦史』については後で詳しく説明する)
2『中古日本治乱記』
山中長俊著
この本の 40、41 巻に、桶狭間合戦のことが記述されている。 古戦場は桶狭間の内、田楽坪とあり、この記の特長は佐々木承禎軍から 2,300 名の 応援隊が織田軍に来ていることである。1 人の学者の 100 巻に及ぶ超編年本のため、 学会では余り信用されていないようである。本当のところは、未だ十分なる検証がな されていないのではないか。
3『信長公記』
古戦場は名古屋市緑区有松町桶狭間 ―桶狭間山及義元最後の地― 桶狭間古戦場公 園とし、作者は大永 7 年(1527)尾張国春日井郡山田安食(現名古屋市西区)に生まれ た太田牛一(通称又助、実名信定、後和泉守と称す)である。 清須城攻撃戦に柴田勝家の家臣として活躍後、弓の腕を見込まれ、浅野又右衛門、 堀田孫七と共に、織田信長の身辺警護役、弓 3 張り衆に抜擢。桶狭間合戦時には 33 歳、信長の息遣いも伺える間近で参陣していたと思われる。 ( 『信長公記』首巻 22 項 に此衆は御手まはりにこれあるなりとある)
あじ き
-4-
�
- ▲TOP