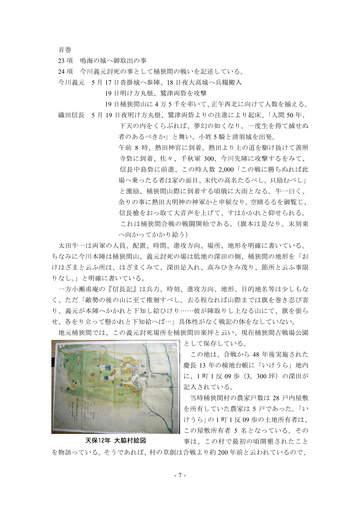桶狭間合戦始末記
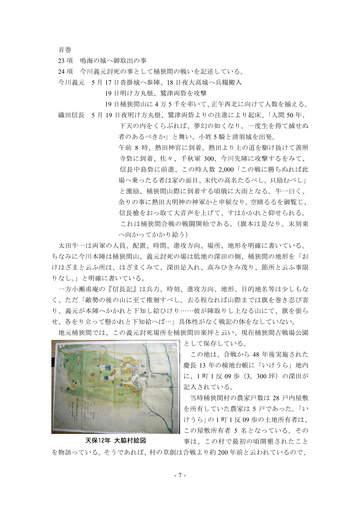
- ページ: 7
- 首巻 23 項 24 項 鳴海の城へ御取出の事 今川義元討死の事として桶狭間の戦いを記述している。 5 月 17 日沓掛城へ参陣、18 日夜大高城へ兵糧搬入 19 日明け方丸根、鷲津両砦を攻撃 19 日桶狭間山に 4 万 5 千を率いて、 正午西北に向けて人数を揃える。 織田信長 5 月 19 日夜明け方丸根、鷲津両砦よりの注進により起床、 「人間 50 年、 下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり。一度生を得て滅せぬ 者のあるべきか」と舞い、小姓 5 騎と清須城を出発。 午前 8 時、熱田神宮に到着、熱田より上の道を駆け抜けて善照 寺砦に到着、佐々、千秋軍 300、今川先陣に攻撃するをみて、 信長中島砦に前進、この時人数 2,000「この戦に勝ちぬれば此 場へ乗ったる者は家の面目、末代の高名たるべし。只励むべし」 と激励、桶狭間山際に到着する頃俄に大雨となる。牛一曰く、 余りの事に熱田大明神の神軍かと申候なり。 空晴るるを御覧じ、 信長槍をおっ取て大音声を上げて、すはかかれと仰せられる。 これは桶狭間合戦の戦闘開始である。 (旗本は是なり。末刻東 へ向かってかかり給う) 太田牛一は両軍の人員、配置、時間、進攻方向、場所、地形を明確に書いている。 ちなみに今川本陣は桶狭間山、義元討死の場は低地の深田の側、桶狭間の地形を「お けはざまと云ふ所は、はざまくみて、深田足入れ、高みひきみ茂り、節所と云ふ事限 りなし。 」と明確に書いている。 一方小瀬甫庵の『信長記』は兵力、時刻、進攻方向、地形、目的地名等は少しもな く、ただ「敵勢の後の山に至て推廻すべし。去る程なれば山際までは旗を巻き忍び寄 り、義元が本陣へかかれと下知し給ひけり……彼が陣取りし上なる山にて、旗を張ら せ、各をり立って懸かれと下知給へば…」具体性がなく戦記の体をなしていない。 地元桶狭間では、この義元討死場所を桶狭間田楽坪と云い、現在桶狭間古戦場公園 として保存している。 この地は、合戦から 48 年後実施された 慶長 13 年の検地台帳に「いけうら」地内 に、1 町 1 反 09 歩(3,300 坪)の深田が 記入されている。 当時桶狭間村の農家戸数は 28 戸内屋敷 を所有していた農家は 5 戸であった。 「い けうら」 の 1 町 1 反 09 歩の土地所有者は、 この屋敷所有者 5 名となっている。その
天保12年 大脇村絵図
今川義元
事は、この村で最初の頃開墾されたこと
を物語っている。そうであれば、村の草創は合戦より約 200 年前と云われているので、
-7-
�
- ▲TOP