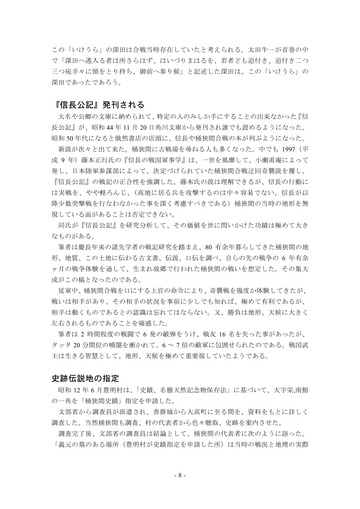桶狭間合戦始末記
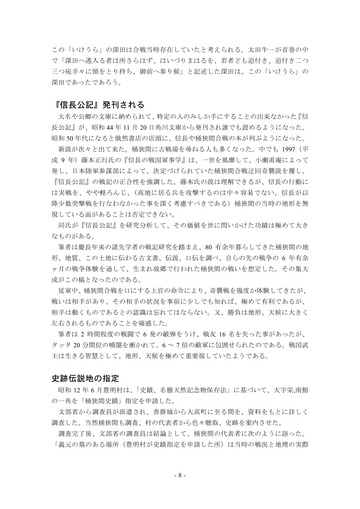
- ページ: 8
- この「いけうら」の深田は合戦当時存在していたと考えられる。太田牛一が首巻の中 で「深田へ逃入る者は所さらはず、はいづりまはるを、若者ども追付き、追付き二つ 三つ宛手々に頸をとり持ち、御前へ参り候」と記述した深田は、この「いけうら」の 深田であったであろう。
『信長公記』発刊される
大名や公卿の文庫に納められて、 特定の人のみしか手にすることの出来なかった 『信 長公記』が、昭和 44 年 11 月 20 日角川文庫から発刊され誰でも読めるようになった。 昭和 50 年代になると俄然書店の店頭に、信長や桶狭間合戦の本が列ぶようになった。 新説が次々と出て来た。桶狭間に古戦場を尋ねる人も多くなった。中でも 1997(平 成 9 年)藤本正行氏の『信長の戦国軍事学』は、一世を風靡して、小瀬甫庵によって 発し、日本陸軍参謀部によって、決定づけられていた桶狭間合戦迂回奇襲説を覆し、 『信長公記』の戦記の正合性を強調した。藤本氏の説は理解できるが、信長の行動に は実戦を、やや軽ろんじ、(高地に居る兵を攻撃するのは中々容易でない。信長が以 降少数突撃戦を行なわなかった事を深く考慮すべきである)桶狭間の当時の地形を無 視している面があることは否定できない。 同氏が『信長公記』を研究分析して、その価値を世に問いかけた功績は極めて大き なものがある。 筆者は慶長年来の諸先学者の戦記研究を踏まえ、80 有余年暮らしてきた桶狭間の地 形、地質、この土地に伝わる古文書、伝説、口伝を調べ、自らの先の戦争の 6 年有余 ヶ月の戦争体験を通して、生まれ故郷で行われた桶狭間の戦いを想定した。その集大 成がこの稿となったのである。 従軍中、桶狭間合戦を口にする上官の命令により、奇襲戦を幾度か体験してきたが、 戦いは相手があり、その相手の状況を事前に少しでも知れば、極めて有利であるが、 相手は動くものであるとの認識は忘れてはならない。又、勝負は地形、天候に大きく 左右されるものであることを痛感した。 筆者は 2 時間程度の戦闘で 6 発の敵弾をうけ、戦友 16 名を失った事があったが、 タッタ 20 分間位の曉闇を衝かれて、6 ~ 7 倍の敵軍に包囲せられたのである。戦国武 士は生きる智慧として、地形、天候を極めて重要視していたようである。
史跡伝説地の指定
昭和 12 年 6 月豊明村は、 「史蹟、名勝天然記念物保存法」に基づいて、大字栄,南館 の一角を「桶狭間史蹟」指定を申請した。 文部省から調査員が派遣され、沓掛城から大高町に至る間を、資料をもとに詳しく 調査した。当然桶狭間も調査、村の代表者から色々聴取、史跡を案内させた。 調査完了後、文部省の調査員は結論として、桶狭間の代表者に次のように語った。 「義元の墓のある場所(豊明村が史蹟指定を申請した所)は当時の戦況と地理の実際
-8-
�
- ▲TOP