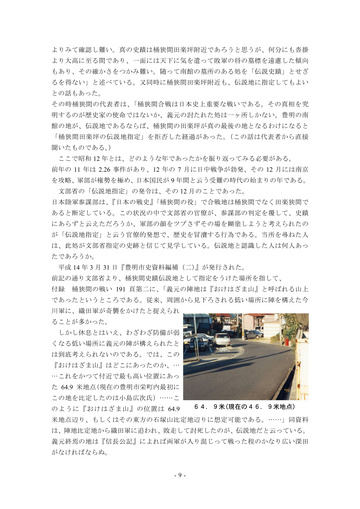桶狭間合戦始末記
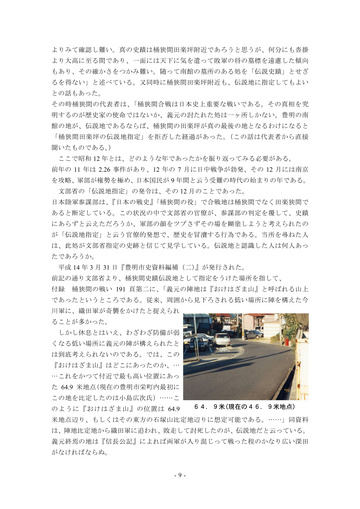
- ページ: 9
- よりみて確認し難い。真の史蹟は桶狭間田楽坪附近であろうと思うが、何分にも沓掛 より大高に至る間であり、一面には天下に気を遣って敗軍の将の墓標を遠慮した傾向 もあり、その確かさをつかみ難い。随って南館の墓所のある処を「伝説史蹟」とせざ るを得ない」と述べている。又同時に桶狭間田楽坪附近も、伝説地に指定してもよい との話もあった。 その時桶狭間の代表者は、 「桶狭間合戦は日本史上重要な戦いである。その真相を究 明するのが歴史家の使命ではないか、義元の討たれた処は一ヶ所しかない。豊明の南 館の地が、伝説地であるならば、桶狭間の田楽坪が真の最後の地となるわけになると 「桶狭間田楽坪の伝説地指定」を拒否した経過があった。 (この話は代表者から直接 聞いたものである。 ) ここで昭和 12 年とは、どのような年であったかを振り返ってみる必要がある。 前年の 11 年は 2.26 事件があり、12 年の 7 月に日中戦争が勃発、その 12 月には南京 を攻略、軍部が権勢を極め、日本国民が 9 年間と云う受難の時代の始まりの年である。 文部省の「伝説地指定」の発令は、その 12 月のことであった。 日本陸軍参謀部は、 『日本の戦史』 「桶狭間の役」で合戦地は桶狭間でなく田楽狭間で あると断定している。この状況の中で文部省の官僚が、参謀部の判定を覆して、史蹟 にあらずと云えただろうか、軍部の顔をツブさずその場を糊塗しようと考えられたの が「伝説地指定」と云う官僚的発想で、歴史を冒瀆する行為である。当所を尋ねた人 は、此処が文部省指定の史跡と信じて見学している。伝説地と認識した人は何人あっ たであろうか。 平成 14 年 3 月 31 日『豊明市史資料編補(二) 』が発行された。 前記の通り文部省より、桶狭間史蹟伝説地として指定をうけた場所を指して、 付録 桶狭間の戦い 191 頁第二に、 「義元の陣地は『おけはざま山』と呼ばれる山上 であったというところである。従来、周囲から見下ろされる低い場所に陣を構えた今 川軍に、織田軍が奇襲をかけたと捉えられ ることが多かった。 しかし休息とはいえ、わざわざ防備が弱 くなる低い場所に義元の陣が構えられたと は到底考えられないのである。では、この 『おけはざま山』はどこにあったのか、… …これをかつて付近で最も高い位置にあっ た 64.9 米地点(現在の豊明市栄町内最初に この地を比定したのは小島広次氏)……こ のように『おけはざま山』の位置は 64.9
64.9米(現在の46.9米地点)
米地点辺り、もしくはその東方の石塚山比定地辺りに想定可能である。……」同資料 は、陣地比定地から織田軍に追われ、敗走して討死したのが、伝説地だと云っている。 義元終焉の地は『信長公記』によれば両軍が入り混じって戦った程のかなり広い深田 がなければならぬ。
-9-
�
- ▲TOP