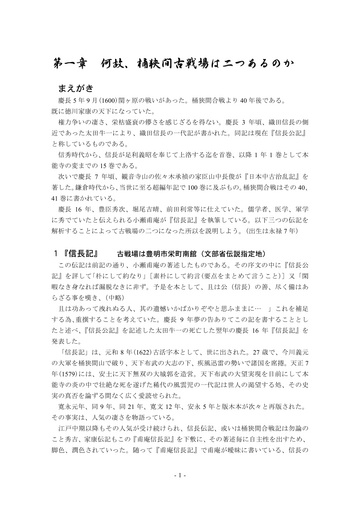桶狭間合戦始末記
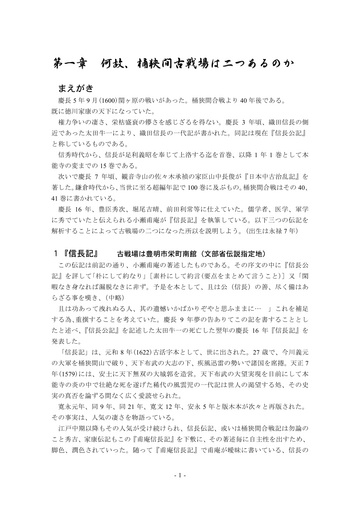
- ページ: 1
- 第一章
まえがき
何故、桶狭間古戦場は二つあるのか
慶長 5 年 9 月(1600)関ヶ原の戦いがあった。桶狭間合戦より 40 年後である。 既に徳川家康の天下になっていた。 権力争いの凄さ、栄枯盛衰の儚さを感じざるを得ない。慶長 3 年頃、織田信長の側 近であった太田牛一により、織田信長の一代記が書かれた。同記は現在『信長公記』 と称しているものである。 信秀時代から、信長が足利義昭を奉じて上洛する迄を首巻、以降 1 年 1 巻として本 能寺の変までの 15 巻である。 次いで慶長 7 年頃、観音寺山の佐々木承禎の家臣山中長俊が『日本中古治乱記』を 著した。 鎌倉時代から、 当世に至る超編年記で 100 巻に及ぶもの。 桶狭間合戦はその 40、 41 巻に書かれている。 慶長 16 年、豊臣秀次、堀尾吉晴、前田利常等に仕えていた。儒学者、医学、軍学 に秀でていたと伝えられる小瀬甫庵が『信長記』を執筆している。以下三つの伝記を 解析することによって古戦場の二つになった所以を説明しよう。(出生は永禄 7 年)
1『信長記』
古戦場は豊明市栄町南館(文部省伝説指定地)
この伝記は前記の通り、小瀬甫庵の著述したものである。その序文の中に『信長公 記』を評して「朴にして約なり」 [素朴にして約言(要点をまとめて言うこと) ]又「閑 暇なき身なれば漏脱なきに非ず。予是を本として、且は公(信長)の善、尽く備はあ らざる事を嘆き、 (中略) 且は功あって洩れぬる人、其の遺憾いかばかりぞやと思ふままに… 」これを補足 する為、重撰することを考えていた。慶長 9 年夢の告ありてこの記を書することとし たと述べ、 『信長公記』を記述した太田牛一の死亡した翌年の慶長 16 年『信長記』を 発表した。 「信長記」は、元和 8 年(1622)古活字本として、世に出された。27 歳で、今川義元 の大軍を桶狭間山で破り、天下布武の大志の下、疾風迅雷の勢いで諸国を席捲。天正 7 年(1579)には、安土に天下無双の大城郭を造営。天下布武の大望実現を目前にして本 能寺の炎の中で壮絶な死を遂げた稀代の風雲児の一代記は世人の渇望する処、その史 実の真否を論ずる間なく広く愛読せられた。 寛永元年、同 9 年、同 21 年、寛文 12 年、安永 5 年と版木本が次々と再版された。 その事実は、人気の凄さを物語っている。 江戸中期以降もその人気が受け続けられ、信長伝記、或いは桶狭間合戦記は勿論の こと秀吉、家康伝記もこの『甫庵信長記』を下敷に、その著述毎に自主性を出すため、 脚色、潤色されていった。随って『甫庵信長記』で甫庵が曖昧に書いている、信長の
-1-
�
- ▲TOP