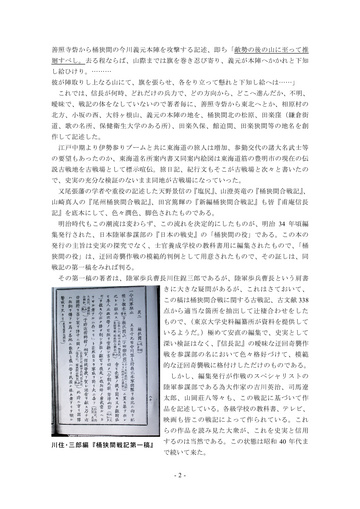桶狭間合戦始末記
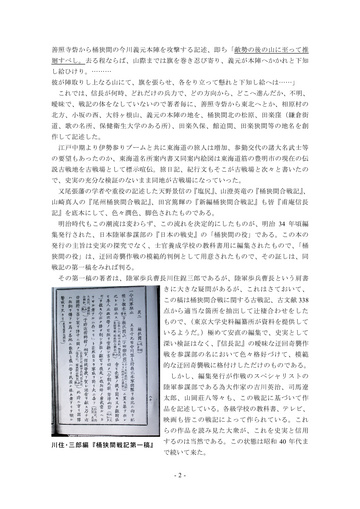
- ページ: 2
- 善照寺砦から桶狭間の今川義元本陣を攻撃する記述、即ち「敵勢の後の山に至って推 廻すべし。去る程ならば、山際までは旗を巻き忍び寄り、義元が本陣へかかれと下知 し給ひけり。……… 彼が陣取りし上なる山にて、旗を張らせ、各をり立って懸れと下知し給へは……」 これでは、信長が何時、どれだけの兵力で、どの方向から、どこへ進んだか、不明、 曖昧で、戦記の体をなしていないので著者毎に、善照寺砦から東北へとか、相原村の 北方、小坂の西、大将ヶ根山、義元の本陣の地を、桶狭間北の松原、田楽窪(鎌倉街 道、歌の名所、保健衛生大学のある所) 、田楽久保、館迫間、田楽狭間等の地名を創 作して記述した。 江戸中期より伊勢参りブームと共に東海道の旅人は増加、参勤交代の諸大名武士等 の要望もあったのか、東海道名所案内書又同案内絵図は東海道筋の豊明市の現在の伝 説古戦地を古戦場として標示喧伝。旅日記、紀行文もそこが古戦場と次々と書いたの で、史実の充分な検証のないまま同地が古戦場になっていった。 又尾張藩の学者や重役の記述した天野景信の『塩尻』 、山澄英竜の『桶狭間合戦記』 、 山崎真人の『尾州桶狭間合戦記』 、田宮篤輝の『新編桶狭間合戦記』も皆『甫庵信長 記』を底本にして、色々潤色、脚色されたものである。 明治時代もこの潮流は変わらず、この流れを決定的にしたものが、明治 34 年頃編 集発行された、日本陸軍参謀部の『日本の戦史』の「桶狭間の役」である。この本の 発行の主旨は史実の探究でなく、士官養成学校の教科書用に編集されたもので、 「桶 狭間の役」は、迂回奇襲作戦の模範的判例として用意されたもので、その証しは、同 戦記の第一稿をみれば判る。 その第一稿の著者は、陸軍歩兵曹長川住鋥三郎であるが、陸軍歩兵曹長という肩書 きに大きな疑問があるが、これはさておいて、 この稿は桶狭間合戦に関する古戦記、古文献 338 点から適当な箇所を抽出して辻褄合わせをした もので、 (東京大学史料編纂所が資料を提供して いるようだ。 )極めて安直の編集で、史実として 深い検証はなく、 『信長記』の曖昧な迂回奇襲作 戦を参謀部の名において色々格好づけて、模範 的な迂回奇襲戦に格付けしただけのものである。 しかし、編集発行が作戦のスペシャリストの 陸軍参謀部である為大作家の吉川英治、司馬遼 太郎、山岡莊八等々も、この戦記に基づいて作 品を記述している。各級学校の教科書、テレビ、 映画も皆この戦記によって作られている。これ らの作品を読み見た大衆が、これを史実と信用
川住鋥三郎編『桶狭間戦記第一稿』
するのは当然である。この状態は昭和 40 年代ま で続いて来た。
-2-
�
- ▲TOP